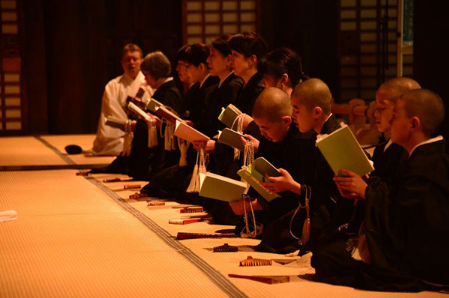常照我
ウサギとカメが競争をし、ウサギが途中で昼寝をしたために、カメが勝った『ウサギとカメ』。
ウサギには「油断大敵」、カメには「地道な努力が大切」との教訓が込められています。
この物語で大切なのは、ウサギとカメがそれぞれ何を見ていたのかです。
ウサギはカメを見ていました。自分より遅い相手だとみると、余裕の構えで昼寝をし、抜かれると追いかけ。それに対してカメは、相手のことを気にすることなく、一歩一歩、歩んでいったのでした。
物語ではカメが勝ちましたが、たとえ負けていたとしてもカメにとっては充実したかけがえのない競争だったことでしょう。
新年度、他人と比べてではなく、自分の中の一番を目指して生活を送りたいものですが。
(機関紙「ともしび」令和2年4月号 「常照我」より)

親鸞聖人のことば
面々の御はからいなり
『歎異抄』より(「佛光寺聖典」七九三頁)
【意訳】
みなさんがた、各自のご判断におまかせするばかりです。
雑談をしていた時のことです。私が言ったことを、いいように受け止められ、恥ずかしいような申し訳なさを感じ、改めて聞く人それぞれの受け止め方だと実感したことがあります。そこで思い出されたのが、「面々の御はからい」という言葉。
自分で決めること
親鸞聖人に直接会って、確かめたいことがあった関東に住むお弟子さんたち。命がけで京都にやって来ます。そんな人たちに、自分が出遇うことができた念仏の教えについて話したあと、「念仏をとりて信じたてまつらんとも、またすてんとも、面々の御はからいなり」。つまり「念仏の教えを信じるのも、捨てるのも、それぞれが自分で決めること」と仰った親鸞聖人は、「信じなさい、そうでないと救われませんよ」とは仰いません。決して押し付けないのです。なぜなら、何を大事にして生きていくのかということは、強制されて決めることではないからです。
安心の上の選択
「自分で決めて」という言葉は、冷たく、無責任に聞こえるかも知れません。けれどもこの言葉の根底には、教えに対する絶対的な安心があるのです。それは、どんな選択をしても大丈夫という安心です。「あなたが阿弥陀という仏を念じる念仏の教えを信じようが、捨てようが、仏はあなたのことを信じ、念じてくれていますよ」ということなのです。
冒頭の話のように、聞き手によって受け止め方が変わるのは仕方がない、という諦めとは違う、安心の上の「面々の御はからい」です。
(機関紙「ともしび」令和2年4月号より)
仏教あれこれ
「桜切るバカ」の巻
あれは自治会の役をしていた十二月の半ば頃でした。張り出した桜の木々の枝々が邪魔だねということになり、とうとう切ることになりました。
「桜切るバカ、梅切らぬバカ」という言葉があります。
桜の木は切り口から腐りやすいので、切り始めは心配しましたが、チェーンソーでサクサク切れるので調子に乗り、結果的にはずいぶんと切り落としました。
一服にお茶を飲み、その戦果の枝木を眺めていた時、突然、若い頃に読んで今はすっかり忘れていた桜にまつわる話を思い出しました。
それは、えもいわれぬほど美しい淡いピンク色に染まった着物を見た人が、「その色は何から取り出したのですか」と染織家に尋ねたという話です。
正解は桜からです。
でも、桜の花びらを煮詰めて取り出したのではありません。黒っぽいごつごつした桜の皮から取り出したもので、しかも、花が咲く直前の頃の樹皮でないとあの美しい色は出ない、確かそんな話でした。
桜は、春という時節に向け、樹木全体で色づくのだと知り、「桜の木も懸命に生きているんや、すごいな」と、若い頃に驚き感心したことが、その時にふいに思い出されたのです。
さて、あの剪定からもう三年が経ちました。桜は、無事に翌年も翌々年も立ち枯れることなく咲いてくれました。今年も満開の美しい花を楽しむことができます。
私はそのおかげで、周りから「バカ」呼ばわりをされることはありません。
(機関紙「ともしび」令和2年4月号より)
おときレシピ Vol.42「里芋のおろしあんかけ」

今回のお料理は里芋のおろしあんかけ。里芋を一度煮て、その後、揚げてからあんかけにします。出汁の味わいと油のコクと香ばしさが存分に楽しめ、腹もちもよい一品です。
この料理を考えるとき、私は先人の弛まぬ努力を垣間見ることができるように思うのです。
里芋の煮物自体はとてもシンプルでスタンダードな料理です。ある意味それで完成していると言ってよいでしょう。それなのに、その完成形である煮物に、あえて粉をうって揚げるという一手間をかける。
さて、食べてみれば確かにおいしい。でも、さすがに油っこい。ならば大根おろしも加えてさっぱりさせてみようか。
なんてことを、どこの誰が考えたのかはわかりませんが、食べることに関する人間の飽くなき探求心が覗えます。
思えばどんなものでも、こうして先人が知恵を絞って作り上げてくれた豊かな食文化に、私たちは生かされ、心と体を育まれているのですね。この料理がこの先さらなる進化を遂げるかもしれないと思うと、未来の食卓に夢が膨らみます。
a
(ワンポイント)
里芋を揚げるときは刷毛などをつかい、薄く片栗粉をつけるといいでしょう。
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

【監修】青江覚峰
一九七七年、東京浅草生。浄土真宗東本願寺派緑泉寺住職。
カリフォルニア州立大学にてMBA取得。料理僧として料理、食育に取り組む。著書に『お寺ごはん』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。NHKをはじめテレビ、新聞などメディア出演も多数。