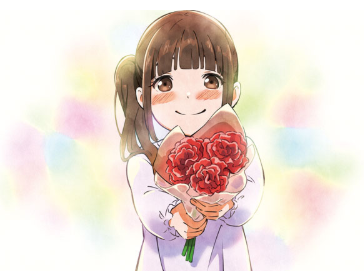常照我
新しいランドセルを背負う一年生。学校という初めての世界に目を輝かせて登校していく。
初心で授業を受ける気持ちはどんなものだろうかと、当時の自分を思い返す。初めてのことに出あったり、新しいことを知った新鮮な感動を覚えている。
ふと今の私は、初心に帰って物事にあたるということを全くしていないことに気付いた。
「仏法は初事として聞け」との言葉がある。同じ法話を聞いてもその時置かれた自分の状況で味わいが全く変わってくる。今のわが身に初めていただく教えと味わう時、そこには新鮮ないのちの感動がある。
それを教えてくださったお念仏の先達方の目は輝いていた。
今という瑞々しいいのちの豊かさを、私もお聴聞の中に味わいたいと感じた。
(機関紙「ともしび」令和6年4月号 「常照我」より)
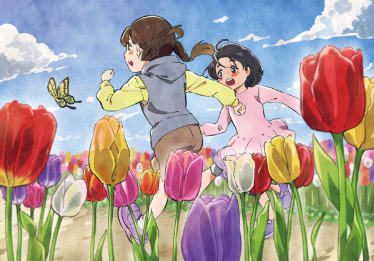
(略歴)成安造形大学メディアデザイン領域CG・アニメーションコース卒業。株式会社ピーエーワークスに約三年勤務。退職後に岡山県真光寺住職を継職。現在は、放課後児童クラブ支援員、イラストレーターを兼業。
親鸞聖人のことば
浄土真宗に帰すれども
真実の心はありがたし
虚仮不実のわが身にて
清浄の心もさらになし
『正像末和讃』より(「佛光寺聖典」六四三頁)
【意訳】
浄土真宗の教えをいただく身になりながらも、わたしに真実の心はなく、その教えを虚しくするわが身であり、清らかな心もまったくありません。
今日は、いつも寺にお参りくださるおばあちゃんのお宅に月参りです。
ああ、ありがたい
お経をいっしょに唱和されると、お茶をいれて下さいました。
「先日はお寺の行事にお参りして、お斎もみんなといっしょにいただいて、おいしかった。ああ、お参りは本当にありがたいですね」とニコニコされます。
ところが急に口調が変わると「聞いて下さいよ。きのう夕方畑から帰ってきたら、じいちゃんがテレビの前でお菓子食べながらごろごろしてるんで、何となくイラッとしました」。話しながら怒りが増すようです。
「汗びっしょりのわたしに、麦茶くれって言ったんですよ。頭にきて、何も答えずシャワーを浴びに行きました。むしゃくしゃして扉をバターンと音立てて閉めてね」。
全く変わらん
ところがおばあちゃんが風呂場から出てくると、じいちゃんは自分で冷蔵庫から出してきた麦茶を飲みながら「寺参りして性格が良くなると思ってたら、全く変わらん」とひと言。そのことばを聞いておばあちゃんはまたヒートアップして「あんたも何も変わらん。わたしの分の麦茶もないし、自分のことばっかり。だいたい結婚したときから……」しばらく売りことばに買いことばだったそうです。
でもお茶をつぎ足しながら一息つくと、おばあちゃんは最後にこうおっしゃったのです。
「長年お参りをしながら、確かにわたしの根性は全く変わりませんね。変わらんことがよくわかりました」。
何かアドバイスをしようと考えていたわたし。そのことばに、わたしの方が打たれたのです。
(機関紙「ともしび」令和6年4月号より)
仏教あれこれ
「謝る姿」の巻
子ども服の量販店で買い物をしていた時、店内アナウンスで私の車の呼び出しがありました。サービスカウンターに向かうと、そこには三十歳くらいの女性の姿が。その方は申し訳なさそうな面持ちで「お車にベビーカーをぶつけてしまいました」と謝ってこられました。
女性の話では、停めていたベビーカーが風で勝手に動いてしまい私の車に当たってしまった、とのことでした。一緒に現場で確認すると、言われなければわからない程度の小さなこすり傷が、かすかにバンパー付近にあるようです。女性は平謝りされ弁償しますと何度も申し出られましたが、気にしないので大丈夫ですと断りました。その時、ふと隣に停まっていた女性の車に目をやると、五、六歳くらいの男の子が車内にいて、お母さんが頭を下げる姿をじっと見つめていたのです。
買い物を終えて帰宅した後も、子どもさんの前で何度も頭を下げる女性の姿がしばらく頭から離れませんでした。次第に、もし逆の立場だったらどうしていただろう、という考えが私の中によぎります。傷は小さく、駐車場に監視カメラもないので、もしかすると私なら黙って帰っていたかもしれません。しかしそれは「悪いことをしても誰も見ていなければ謝らなくてもいいんだよ」と子どもに態度で教えているようなものです。
親がどのように生きているかをありのままに子どもは見ています。正直な子に育って欲しいという子どもへの願いは、同時に、私自身が誠実であるだろうかという自分への問いでもあるのだ、と気付かされた出来事でした。
(機関紙「ともしび」令和6年4月号より)
おときレシピ Vol.82「人参とセロリの柚子胡椒ラペ」

フランス料理で前菜としてよく使われる人参のラペですが、「ラペ」とはもともと「チーズのおろし金を使って細く切る」ことを指すものだそうです。この切り方をしたものであればなんでも「ラペ」になるのですが、例えば「人参のラペ」でも、スパイスやドライフルーツ、またナッツを加えたりとアレンジは様々。シンプルながらも地域や家庭によって変化があるのが面白いですね。
私たちの仏教も同じです。同じ浄土真宗でも北陸と関東、関西、広島など地域によって、お盆の迎え方や報恩講の御供物などが異なります。
しかし、どんな味付けをしてもラペはラペであるように、どのような作法があっても報恩講は報恩講であり、信仰は信仰です。
違いがあるからこそ本質が尊く感じられるものです。
(ワンポイント)
塩と柚子胡椒の分量で辛さなどを調整できます。
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

【監修】青江覚峰
一九七七年、東京浅草生。浄土真宗東本願寺派緑泉寺住職。
カリフォルニア州立大学にてMBA取得。料理僧として料理、食育に取り組む。著書に『お寺ごはん』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。NHKをはじめテレビ、新聞などメディア出演も多数。