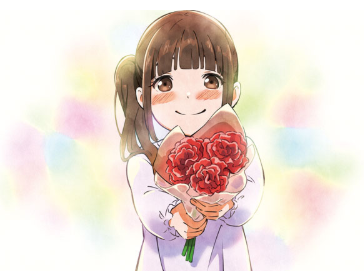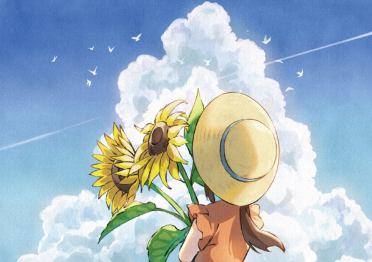常照我
私が幼い頃の映像を見た。泣いている六歳の私。今は亡き父が、何とか私の機嫌を直して一緒に遊ぼうと、根気強く応じてくれていた。そんな光景を、私は映像を見るまで忘れていた。
阿弥陀さまの慈悲がそそがれる様子を雨にたとえて、お経には「法雨を澍ぐ」とある。
この「そそぐ」は「樹」に水を表す「氵」の字があてられる。
どんな大樹もはじめは苗木である。大きく育ったのは、そこに絶えることなく慈雨がそそがれ続けてきたからである。
私は父によく遊んでもらったが、覚えていないことばかりだ。私がしてもらったと認識しているご恩はほんのわずかなのだ。
阿弥陀さまの法の雨は、今も私にそそがれ続けている。私は今ほんの少しそのご恩に気づいて、手を合わせている。
(機関紙「ともしび」令和6年7月号 「常照我」より)
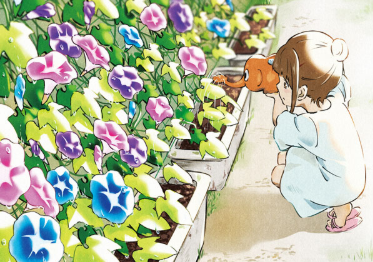
(略歴)成安造形大学メディアデザイン領域CG・アニメーションコース卒業。株式会社ピーエーワークスに約三年勤務。退職後に岡山県真光寺住職を継職。現在は、放課後児童クラブ支援員、イラストレーターを兼業。
親鸞聖人のことば
有情の邪見熾盛にて
叢林棘刺のごとくなり
『正像末和讃』より(『佛光寺聖典』六二七頁)
【意訳】
人々の邪なものの見方は、火のように激しく燃え盛り、まるで草むらや林を覆う茨のトゲが生い茂るかのように充満しています。
思い込み
私は製造業の会社に勤務しているのですが、先日、ある製品の部品をめぐって論争が起きたことがありました。部品の加工法がAかBか、というもの。
私はその製品の立ち上げから関わっていましたので、自信満々に「当初からずっとAが使われています。図面上のBというのは誤記です」と主張。しかし相手側は「それはおかしい、図面にある通りのBが正しいはず」と譲らず。何回か応酬が続き、他部門も巻き込んでだんだん話が大きくなっていきました。
私はムキになり、図面改訂や部品選定の経緯を時系列に沿って再確認したところ、「あれ?」試作時は確かにAで試みていたものの、途中でBに変更していた事実が判明。なんとも盛大な思い違い、それを堂々と主張して、お恥ずかしい限りです。
邪見というトゲ
この時は誤認を素直に謝罪し事なきを得ましたが、全社的な大問題に発展する一歩手前でした。自分は悪くないと固執していたら、関係をこじらせ、信頼を失っていたことでしょう。
自分が正しいと思い込み、イライラを抱えて苦を生み出す。それを他者にも向け、ぶつかりあってしまうのです。
そんな姿をズバリ言い当てているのが、自らも周囲も傷つけてしまう邪見のトゲが生い茂っている、という親鸞聖人のお言葉です。ひいては仏さまの教えに対しても、救いなど本当にあるのかと、疑いのトゲを向けてしまうのです。
この悲しきトゲを抱えて生きる身であると自分事として受け止めよ。そんな呼びかけとして、聖人は邪見について繰り返し説かれているのでしょう。
(機関紙「ともしび」令和6年7月号より)
仏教あれこれ
「断捨離vsもったいない」の巻
モノの整理や処分ができずに室内が物置化しています。早く断捨離をせねばと思い、何年も過ぎています。最近は妻とその話題が多いです。ただ、その場合は家の改修問題もからんでくるので、腰がもっと重くなってしまうのですが。
子ども時代、母や祖母からしきりと聞かされた小言は、「もったいない」の言葉だったなと思い出されます。残さず食べなさい。モノは使い切りなさい。使えるモノは捨てずに残しなさい。ていねいに扱いなさい等々。身に付いたこの筋金入りの価値観で、モノが捨てられないのだと、かってに自己弁護をしています。
車を買い換えましたが、前の車は実に二十三年乗りました。ただ十三年目以降は自動車税が上がり不満でした。むしろ逆に、大切にしているごほうびで下がるのではと期待していたのに。現代は、モノを大切に長く使う社会ではないのでしょう。
二十年ほど前です。ケニアのワンガリ・マータイさんが感銘を受けた日本語の「MOTTAINAI」を、環境を守る世界の共通語にしようと大々的に提唱されましたが、今はすっかり忘れられたようです。
現代は消費社会なのに、どうして私の家の中はモノだらけになっているのだろう? 昔は貧しく、モノも少ない社会だったかもしれないけれど、子どもの頃の、あのすっきりとしていた家がうらやましくもなります。
まあ何にせよ、本当に始末上手な人なら、こんなご託を並べる前に片づいているでしょう。
(機関紙「ともしび」令和6年7月号より)
おときレシピ Vol.84「ごま冷や汁」

食欲が落ちぎみになる暑い時期。水気と一緒にサラリと食べて栄養も摂れるものがありがたいですね。
そうめんなどの冷たい麺もいいのですが、麺を茹でるのも億劫なときにぜひ作っていただきたいのがこちらの冷や汁です。前の日のご飯を少し取り分けて冷蔵庫に入れておき、野菜を切ってお出汁をかけるだけという手軽さでありながら栄養価も高く、さっぱりと頂けます。
鎌倉時代の『鎌倉管領家記録』に「武家にては飯に汁かけ参らせ候、僧侶にては冷汁をかけ参らせ候」との記載があるように、僧侶によって全国に伝わり、その影響で宮崎県に広まったと言われています。この冷や汁、お寺との深いご縁を思いながらお召し上がりください。
(ワンポイント)
豆腐を少し水切りしてから崩すと味わいが濃くなって一層楽しめます。
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

【監修】青江覚峰
一九七七年、東京浅草生。浄土真宗東本願寺派緑泉寺住職。
カリフォルニア州立大学にてMBA取得。料理僧として料理、食育に取り組む。著書に『お寺ごはん』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。NHKをはじめテレビ、新聞などメディア出演も多数。