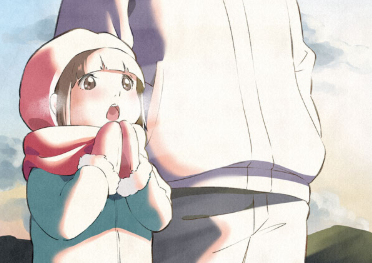常照我
いつも三月花の頃
お前十九でわしゃ二十歳
死なぬ子三人親孝行
使って減らぬ金百両
死んでも命が
ありますように
江戸時代に詠まれた戯歌である。私たちが常に思い描く願いを端的に表している。歌の文句とは裏腹に、寒暑、貧困、老死といった不都合を生きねばならない。娑婆を生きる悲哀を笑いに昇華した歌といえよう。
仏教では諸行は無常であると説く。すべての物事は必ず移ろいゆくという意味だ。しかし、私の思いは、無常の事実を素直に認めることができない。戯歌のような願望に必死にしがみつき、理想と現実との乖離に苦悩を抱えてしまう。
悩み苦しむ衆生を誰よりも憐れむ方を仏という。春彼岸は仏の大悲のお心を聞くご縁である。
(機関紙「ともしび」令和7年3月号 「常照我」より)

(略歴)成安造形大学メディアデザイン領域CG・アニメーションコース卒業。株式会社ピーエーワークスに約三年勤務。退職後に岡山県真光寺住職を継職。現在は、放課後児童クラブ支援員、イラストレーターを兼業。
親鸞聖人のことば
ただ念仏して
弥陀にたすけられまいらすべし
『歎異抄』より(『佛光寺聖典』七九二頁)
【意訳】
ただ念仏することを願われていることが、阿弥陀仏の大悲なのです。
先日、あるご家族の法事が本堂でつとまりました。久しぶりに集まられたようで、お茶を飲み、楽しく歓談している時でした。
小学生の男の子が「お父さん、人は死んだらどうなるの」と聞きました。父親はすかさず「死んだら終いや」と答えていました。
さて、そうなのでしょうか。
大悲に生きる人とあう
お釈迦さまのお弟子に阿難という人がいました。とてもやさしくて、常にお釈迦さまのそばでお説教を聞いているのですが、覚りには至っていませんでした。
ある日、阿難はお釈迦さまの前で突然立ち上がり、お釈迦さまの光り輝いているおすがたを褒めたたえたのです。
そして、その理由を「私たちは、常に仏さまに成ることを願われている存在だと、お釈迦さまはお説きになられていたのですね」と、言いました。
阿難にはこの時、初めていまを生きるということへの問いが生まれたのです。何がおこるかわからない未来に不安を抱き生きるのではなく、仏さまの願いに応えているのか問われながら生きる存在だと教えられたのです。
それは、お念仏に生きる私たちも同じです。
願いに生きる人となる
現代は、便利で豊かな暮らしになりながら、先行きに不安を感じることが多くなりました。それを解決するかのように健康食品、器具、サプリメント、保険の宣伝等が多く見受けられます。
上記のことばから、「死んだら終いや」ではなく、亡くなっていかれた方の願いに気づき、はげまされ、生かされていることを教えられるのです。
親鸞聖人は、その願いが届いていることを気づかせてくださるのが、お念仏だとお伝えくださっているのです。
(機関紙「ともしび」令和7年3月号より)
仏教あれこれ
「励ましの力」の巻
ハンバーガーを買おうと並んでいたときです。すごく大きな声が聞こえました。一番前の男の人が、店員さんに向かって、「おい、何しとるんや。早うせえ。いつまで待たせとるんや。」と、何度も大声で怒鳴っていたのです。アルバイトらしい若い店員さんは、「すみませんでした」と、商品を渡した後も、出ていく男の後ろ姿に何度も頭を下げていました。
その時のハンバーガーの店にいたお客さん達は凍りついたようになり、嫌な雰囲気になりました。それでもその店員さんは気持ちを取りなおして、次のお客さんに、無理矢理つくった笑顔で、「いらっしゃいませ。ご注文は何になさいますか?」と、尋ねていました。
その時です。その次の年配のお客さんが、「君、えらいな。世の中には自分の思い通りにならんと怒鳴る人がいるんやなあ。つらい思いをしたのに、君は今、私に笑顔で注文を聞いてくれている。ありがとう。」と言われたのです。また、となりにいたおばさんからは、「あなた、頑張ったわよ。」と励まされたのでした。
すると、それまでぐっと我慢していた店員さんの目から大粒の涙があふれました。
とげとげしかった店の空気も、その声かけで、いっきに変わったように感じました。私が注文する時には何もなかったような元の様子に戻っていました。
(機関紙「ともしび」令和7年3月号より)
おときレシピ Vol.91「いちごのすりながし」

「すりながし(擂り流し)」とは、野菜や魚介などの食材をすりつぶして出汁でのばした料理を指します。このコーナーでも何度か紹介しましたが、今回はこれまでとはがらりと趣向を変えて「いちごのすり流し」をご紹介します。
作り方はいたって簡単です。いちごに甘酒や砂糖を加えてミキサーにかけ、器に注ぐだけ。手順はこれだけのシンプルな料理ですが、いちごの色や香りが実に心華やぐご馳走に早変わり。
そもそも料理とは材料の「料」と調理の「理」を合わせた言葉と言われています。単に食材を並べるだけではなく、素材を弄過ぎることもなく、ちょうど良くバランスが取れていること。
「すりながし」はまさにそんな料理だと言えるでしょう。
(ワンポイント)
砂糖の量は、いちごの甘さなどで調整をするとよいでしょう。
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

【監修】青江覚峰
一九七七年、東京浅草生。浄土真宗東本願寺派緑泉寺住職。
カリフォルニア州立大学にてMBA取得。料理僧として料理、食育に取り組む。著書に『お寺ごはん』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。NHKをはじめテレビ、新聞などメディア出演も多数。